都議会公明党実績紹介
![]()
厚生労働省によれば、ヤングケアラーとは法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に
行っている子どもとされています。
厚生労働省と文部科学省による調査によると、中学2年生の約17人に1人、高校2年生では、24人に1人が世話をする家族が「いる」との回答がありました。
この現状をふまえ、区議会公明党は、第2回定例会の代表質問で、「ヤングケアラーの支援調整の窓口設置」「各種の行政や団体のネットワークを通じて連携を強化すること」「ヤングケアラーの認知度の向上」を新宿区に要望しました。
新宿区におけるヤングケアラーの相談は、子ども総合センターと4所の子ども家庭支援センターで「子どもと家庭の総合相談」の中で対応されています。
今後、新宿区は、「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」による連携の強化や、子ども食堂や学習支援等で子どもと関わる民間団体等に見守りを依頼するなど、ヤングケアラーを支援する取り組みを推進することを表明しました。
![]()
【相談受付時間】 月曜〜土曜 午前8時30分〜午後7時まで(電話・来所)
日曜・祝日 午前8時30分〜午後5時まで(電話のみ)
相談専用電話: 03(3232)0675 FAX: 03(3232)0666
![]()
 ●中落合(なかおちあい)子ども家庭支援センター
●中落合(なかおちあい)子ども家庭支援センター
相談専用電話: 03(3952)7752
●榎町(えのきちょう)子ども家庭支援センター
相談専用電話: 03(3269)7345
●信濃町(しなのまち)子ども家庭支援センター
相談専用電話: 03(3357)6855
●北新宿(きたしんじゅく)子ども家庭支援センター
相談専用電話: 03(3362)4152
![]()
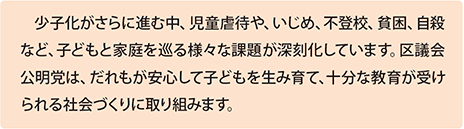
公明党は、第二回定例会の代表質問で、 子どもの権利擁護について質問しました。子どもの意見を区政に反映できるような仕組みづくりや、子どもの命を守るため、福祉・医療・教育・警察等のネットワークの強化を求めました。
また、ひとり親世帯の貧困の要因とも指摘される養育費の不払い問題についても対応を求めました。新宿区は、区のひとり親世帯の特性に応じた支援策を検討することを明らかにしました。
![]()
長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、区内の消費が著しく低下しています。区議会公明党は、感染拡大を抑えワクチン接種を推進するとともに、区民の消費生活を支え、区内中小事業者を支援する取組を繰り返し要望してきました。
キャッシュレス決済によるポイント還元の実施とともに、デジタル対応の恩恵が行き渡らない方々のために、
紙媒体によるプレミアム付き商品券の発行も求めてきました。
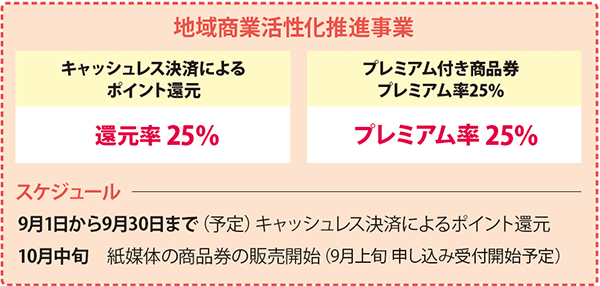

![]()

区議会公明党は、これまでLGBT等性的マイノリティの方との意見交換やアンケート調査を実施し、理解の促進と支援の充実に取り組んできました。当事者の方からは、「誰にも相談ができなかった」、「将来のロールモデルが持てない」など、切実な声を頂きました。現在、東京都では、パートナーシップ制度の検討が進められています。区議会公明党は、第二回定例会の代表質問で、都の動向を注視して、これまで以上に「性の多様性」の理解促進と支援を推進していくことを求めました。
区は、公明党の要望に対して、性的マイノリティの方の、行政サービスにおける課題を解消することが必要と認識していることを述べ、まずは、都の動きなども踏まえ区立住宅における入居資格の確認方法等、入居者要件の見直しについて検討することを表明しました。
新宿区では、令和4年1月に区職員の理解を促進する「職員向けのハンドブック」の発行及び、令和4年3月には性の多様性や人権尊重の大切さについて子どもたちの理解が深まるよう「小学生向けの啓発誌」発行などが予定されています。
これからも公明党は性の多様性の理解を促進するために、全力で取り組みます。